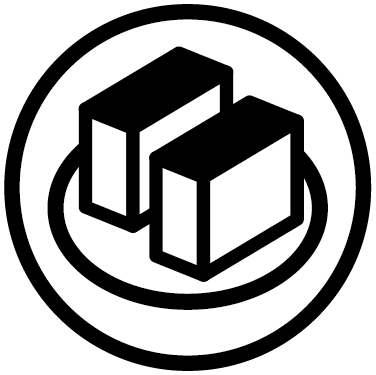ストーリー
コーヒー豆を美味しいまま保存するための4つのポイント|買い方のコツも解説
コーヒー豆を美味しいまま保存するための4つのポイント|買い方のコツも解説

コーヒー豆の正しい保存方法を知っておくと、毎日の一杯をより美味しく楽しめるようになります。
この記事では、自宅で美味しいコーヒーを淹れたい人に向けて、コーヒー豆を保存するときに注意すべきポイントや、買い方のコツ、冷凍保存の是非などを解説します。コーヒーが好きな人は、ぜひお役立てください。
--------------------------------------------------
📖目次
- コーヒー豆は「乾物」ではないため適切な方法で保存を
- コーヒー豆を美味しいまま保存するための4つのポイント
- コーヒー豆は冷凍保存がよい?
- コーヒー豆の家での保存期間の目安
- コーヒー豆の劣化を防ぐための買い方
- コーヒー豆の保存容器の特徴と注意点
- まとめ
--------------------------------------------------

コーヒー豆は「乾物」ではないため適切な方法で保存を
コーヒー豆は、その見た目から「乾物」のようなイメージを持たれやすく、あまり劣化しないものと考えている人もいます。
実際、コーヒー豆は長い期間置いても、野菜のように腐ったり萎びたりするような見た目の変化はほぼありません。
しかし、実はコーヒー豆は鮮度が重要なデリケートな食品です。
劣化してしまうと香りや風味が損なわれてしまうため、最後まで美味しく飲むためには適切な方法で保存する必要があります。
🔍コーヒー豆の劣化とは
コーヒー豆が湿度や紫外線、空気に触れることなどの影響によって劣化し、香りが失われたり、風味が変化したりします。
コーヒー豆は、油分が多く含まれている食品です。
そのため、時間が経つとこの油分が酸化し、エグミや雑味が出る、ツンとした酸味を感じるようになるなどの変化が生じることもあります。
こうした性質から、コーヒー豆は野菜や魚などの生鮮食品と同じく、保存方法が美味しさを保つうえで重要です。
コーヒー豆を美味しいまま保存するための4つのポイント
続いて、コーヒー豆の劣化を防ぎ、美味しさを長く保つために気をつけたい保存のポイントを4つご紹介します。
どれも家庭で簡単に取り入れられる方法ばかりなので、ぜひ参考にしてみてください。
1.高温を避けて保存する
コーヒー豆は、高温下に置いておくと、表面の油分の酸化が早まってしまうため、保存場所には注意が必要です。
保存場所の温度が高いと、コーヒー豆の劣化が進んでしまう恐れがあります。
そのため、高温の場所を避け、できるだけ温度変化の少ない場所で保存することが大切です。
特に暑い時期には注意しましょう。
2.光を避けて保存する
コーヒー豆に太陽光が当たると、豆の温度が上昇し、高温環境と同様に劣化の原因になります。そのため、光を避けて保存することが大切です。
また、太陽光だけでなく、照明の光も劣化の一因となる可能性があるため注意しましょう。
たとえば、照明の当たらない暗いパントリーに保管したり、光を遮るアルミ素材の保存袋を使ったりすることで、光の影響を抑える工夫ができます。
3.多湿を避けて保存する
コーヒー豆が湿気にさらされると、酸化が進んで風味が損なわれるほか、豆の成分が変質する可能性があります。
さらに、保存場所の湿度が高すぎると香りや味が変化するだけでなく、水滴が付着してカビの原因になることもあるため、十分な注意が必要です。
水回りなど湿度が高くなりやすい場所は避け、風通しがよく湿度の低い場所で保存しましょう。
4.酸素に触れないように保存する
空気中の酸素にコーヒー豆が触れてしまうと、酸化によって香りが飛んだり、周囲の匂いが移ったりするなどの劣化が起こりやすくなります。
特に、粉の状態のコーヒーは豆に比べて表面積が大きいため、酸化の影響を受けやすいとされています。
そのため、できるだけ酸素に触れないよう、密閉容器(キャニスターなど)を使って保存することが重要です。
コーヒー豆は冷凍保存がよい?
コーヒー豆は、高温や光を避けられるという理由から、冷凍庫での保存を推奨されることがあります。
確かに冷凍庫内は温度が低く、光も遮断されるため、劣化を抑えやすい保存環境といえます。
ただし、冷凍保存には注意点もあります。
冷凍庫から豆を取り出した際に、温度差によって表面に結露が発生し、湿気を帯びてしまう可能性があるためです。
特に夏場のように外気との温度差が大きい時期は、取り扱いに気をつけましょう。
冷凍保存をする際は、使う分だけを小分けにして密閉容器に入れ、一度取り出した分はすぐに使い切るのが理想的です。
冷蔵庫保存も同様で、温度差による結露や他の食品の匂い移りが起こりやすいため、必ず密閉容器に入れて保存することが大切です。
コーヒー豆の家での保存期間の目安
コーヒー豆を適切な温度や湿度、容器で管理した場合の保存期間の目安は、以下の通りです。これらの条件を守ることで、豆の鮮度と風味をより長く保つことができます。
☕豆で購入した場合
アルミバッグなど光を遮る容器に密封された未開封のコーヒー豆の保存期間は、約1か月から数か月が目安とされています。
ただし、冒頭でも解説したように、コーヒー豆は鮮度重視のデリケートな食品です。
保存期間の目安は長めですが、美味しく飲むためにも開封後1か月以内を目安に飲み切ることをおすすめします。
☕粉で購入した場合
コーヒーは粉の状態だと劣化が進みやすいため、保存期間に注意が必要です。
粉で購入した場合の保存期間は、未開封なら約2週間、開封後は1週間以内が目安とされています。
豆に比べて劣化が早く進むため、粉で購入する際は必要な分だけ買うよう心掛け、保存期間内であってもできるだけ早く飲み切りましょう。
コーヒー豆の劣化を防ぐための買い方
コーヒー豆の劣化を防ぐためには、買い方にもコツがあります。コーヒー豆を購入する際は、以下に注意しましょう。
💡できれば豆の状態で買う
コーヒー粉は豆の状態に比べて表面積が大きいため、空気に触れることによる劣化が起こりやすいです。
もし家にコーヒーミルなど豆を挽く器具があれば、豆の状態で購入し、飲む直前に挽くことをおすすめします。
豆の状態であれば、風味が損なわれにくく、保存もしやすくなります。
ただし、一度にたくさん挽いて粉の状態で保存してしまうと、香りや味わいが落ちてしまうため、必要な分だけその都度挽くのが理想的です。
💡短期間で飲み切れる量を買う
コーヒー豆は、どんなに保存方法に気を配っていても少しずつ劣化が進んでいきます。そのため、保存期間が長い豆の状態で購入する場合でも、香りや味を存分に楽しみたいなら2週間程度で飲み切れる量を目安に購入するのがおすすめです。短期間で飲み切れる量だけ買えば、最後までよい品質で美味しく飲めるでしょう。
💡信頼できるお店で買う
コーヒーを最後まで美味しく楽しむには、コーヒー豆が新鮮な状態で売られている、信頼できるお店で購入することも大切です。
たとえば、店内やコーヒー豆のケースが清潔かどうか、日光の当たる場所にコーヒー豆を置いていないかなどをチェックしましょう。
コーヒー豆が清潔に保たれ、鮮度を落とすような場所で販売されていないかも重要なポイントです。
また、自家焙煎かどうか、焙煎日が近いかも確認しましょう。
自家焙煎であれば焙煎士が店頭にいらっしゃる場合は直接質問や要望を聞いてくれることもあります。
焙煎日は新しいほど新鮮な状態で、焙煎日が近いとより長く味わえます。
なお、Webで購入する場合は、ホームページなどでショップのこだわりを確認しましょう。
💡お店の人に話を聞く
もしお店の人に質問できる状況であれば、コーヒー豆の保存方法や保存期間について尋ねるとよいでしょう。
コーヒー豆は焙煎度合いや状態によって保存できる期間が異なります。
たとえば、浅煎りは特徴的な風味が繊細なため、時間の経過による変化がわかりやすいですが、深煎りの香ばしい風味は劣化しにくい場合が多いです。
お店によって焙煎度合いも違いますので、購入を検討しているコーヒー豆について直接質問してみるのもおすすめです。
コーヒー豆の保存容器の特徴と注意点
遮光性の高いチャック付きの袋を使っているお店のコーヒーはそのままその袋を保存用にしてかまいません。
密閉できない袋のコーヒー豆を買ったときは、コーヒー豆を容器に移し替えて保存するのがおすすめです。
よく使われる保存容器の特徴と注意点は以下の通りです。
🫙コーヒーキャニスター
コーヒーキャニスターは、コーヒーの保存に適した専用の保存容器であるためおすすめです。
ただし、ひとくちにコーヒーキャニスターといってもさまざまな種類の形状があります。
たとえば、フタにパッキンがあるものやフタが二重構造になっているものは密閉性が高いです。
商品を選ぶ際には、見イズだけでなく密閉性の高さもチェックしましょう。
また、コーヒー豆は直接キャニスターに入れるのではなく、購入したときの袋のまま入れると、より劣化を防げます。
その際、袋の口は輪ゴムやテープでしっかり閉じて密封しましょう。
🫙ガラスのビン
ガラスのビンは見た目がおしゃれで、コーヒー豆を入れる容器として人気があります。
ガラスのビンであれば、どれくらいコーヒー豆が残っているかも一目で確認できます。
しかし、ガラスのビンは陶器製やホーロー製と違い遮光性が低く、光を通しやすいのがデメリットです。もしガラスのビンにコーヒー豆を保存したいのであれば、色のついたガラスのものにしたり、光の当たらない場所に保存したりといった工夫が必要となります。
まとめ
冒頭で解説したように、コーヒー豆は鮮度が重要な食品です。保存場所の温度や湿度、光などに配慮しないと、コーヒー豆が劣化してしまうおそれがあるため、取り扱いには十分注意しましょう。
コーヒー豆の劣化を防ぐためには、買い方や保存容器の選び方にも工夫が必要です。
コーヒー豆を購入するときは、豆の種類や保存容器にも気を配るとよいでしょう。
なお、猿田彦珈琲ではさまざまな種類のコーヒー豆を取り扱っており、こだわりの機能が備わった使いやすいパッケージで飲み比べセットなども展開しています。
コーヒーが好きな方はぜひチェックしてみてください。